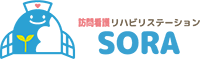在宅療養コラム~パーキンソン病編その2
SORAではパーキンソン病の方へ看護とリハビリで連携してアプローチを行っています。
初めに、看護のアプローチについてご紹介させていただきます。
日々関わらせていただいているAさんへの看護を通して、どのような支援を行っているかをお伝えできればと思います。
Aさんは70代の男性で、ご自宅でご家族と過ごしながら訪問看護を利用されています。
動作は徐々にゆっくりになっていますが、「できることは自分でしたい」という思いを大切にされている方です。
看護師のアプローチ
Aさんとの関わりの中で、私たちが特に意識しているのは、
排泄の支援(便秘)、転倒予防(低血圧)、食事支援(嚥下機能)、服薬管理の4つです。
パーキンソン病は運動症状だけでなく、気分の変化なども含めさまざまな面に影響を及ぼす疾患です。
そのため、「その人らしさ」を大切にしながら、個別性の高いケアを提供することが求められます。
【1. 排泄支援:“出たかな?”に寄り添う】
パーキンソン病における便秘は非常に多くの方に見られ、運動症状よりも早期に現れることもある重要な非運動症状です。
Aさんは以前から便秘傾向があり、排便がない日が続くと腹部膨満感(お腹の張り)や食欲の低下が見られました。
そのため訪問時には毎回、「今日は出ましたか?」と排便状況の確認を行い、表情や腹部の状態からも様子を観察するよう心がけることを意識していました。
便秘が続く場合は、医師の指示のもと下剤の使用について助言を行い、必要時には摘便や浣腸を実施することもあります。
【2. 転倒予防:ふらつきを“防ぐ”支援】
Aさんは起立性低血圧の傾向があり、これまでに何度か転倒を経験されています。
立ち上がりや移動の際には、「寝た状態→座る→立つ」といった段階的な動作を心がけるようお伝えしています。
またリハビリスタッフと連携し、下肢筋力の維持や、急な血圧変動を防ぐための運動指導も行っています。
ご家族には、「夜間のトイレ動作」や「朝の起床時」など転倒リスクが高まる時間帯について、注意して見守っていただくようお願いしています。
【3. 食事支援:安心して“食べる”ための工夫】
嚥下障害はパーキンソン病の進行に伴い高頻度で現れる非運動症状で、誤嚥性肺炎や低栄養、脱水のリスクにつながる重大な問題です。
訪問看護では、早期発見・予防・ご家族への指導が非常に重要な役割となります。
Aさんの場合、水分摂取時にむせることがあり、とろみ剤の使用を勧めることで誤嚥の予防を図っています。
また、「一口の量を少なく」「姿勢はやや前傾に」「口に入れたら意識してゆっくり飲み込む」など、具体的なアドバイスを行っています。
ご家族とも一緒に、Aさんが食べやすい食形態や、好みに合ったやわらかい食事について相談しながら工夫を重ねています。
【4. 服薬支援:忘れないための“見える化”】
パーキンソン病の治療では、薬の内服時間が症状のコントロールに大きく影響します。
そのため、服薬管理は訪問看護における非常に重要な支援のひとつです。
Aさんは以前、薬の飲み忘れにより動きにくさやふらつきが強まる日がありました。
ご本人・ご家族と相談し、一週間分の薬を朝・昼・夕で分けて管理できる服薬カレンダーを導入しました。
導入後はご自身でカレンダーを確認しながら服薬できるようになり、「これがあると安心するね」とお話しされています。
リハビリのアプローチ
次にリハビリでのアプローチについてご紹介させていただきます。
【リハビリ:身体機能・歩行能力の維持】
Aさんは、「歩いて移動したい」という希望が強い方でした。
パーキンソン病の症状が時間帯や日によって異なるため、転倒防止を図るために歩行器の提案をしました。
しかし、自分の力で歩きたいという思いが強く、それには頼りたくないとお話があり、杖か壁などの伝い歩きで移動されています。
Aさんの思いを尊重し、それに応じたリハビリプログラムと実際の45分間の訪問の流れもお伝えします。
-
バイタル測定 5分
起立性低血圧があるため、血圧の変化は注意しています。
血圧が低い場合はベッド上で運動してから、椅子での姿勢に戻り、運動を再開することがあります。
-
発声練習と口腔体操 10分
呼吸での気流量が弱くなることを防ぐため深呼吸の練習と声量が保てるよう発声の練習をしていただきます。
口腔体操は一般的に行われる「パタカラの発声」や「口唇の運動」を行っていただいています。
-
下肢筋力トレーニングとバランス練習 15分
歩行中のふらつきがあり、すり足歩行となることが多いため、転倒の危険性が高くなっています。
また、歩行中の足と足の間隔が狭くなり、足が重なり合ってバランスを崩す様子がみられます。
歩幅が狭くなることに対しては「前方ステップと側方ステップ」を行い、歩幅を広げることに慣れ、動作中のバランスが保てることを目的にしています。
現在、支持物は持たずにフリーハンドで前方ステップを左右10回、側方ステップを左右10回実施しています。
その他のバランス練習では片脚立位を実施していただいています。
-
歩行練習と段差昇降15分
先ほど紹介した通り、Aさんの歩行の特徴として左右の足の幅が狭くなり、足が内側に入るため、足と足がぶつかってしまいます。
そのため、立ち上がり動作前に足を肩幅に開くよう注意してもらい、歩行中に姿勢を正すことと同時に足を着く位置は常に肩幅になるよう声掛けしています。
歩行バランスが一定でないため、足の接地位置がずれてしまう事もあり、ご本人にはバランスを補うため歩行器の使用も勧めています。
道路から自宅玄関までのアプローチに階段があるため、段差昇降練習も行っています。
現在は階段の1段目を使用し、右足からの昇りを10回、左足からの昇りを10回の練習を行っていただいています。
以上が大まかなリハビリの内容と流れになります。
もちろん疲労が出現するため、すべてのプログラムを連続して行うことはなく、疲労に応じて休息を取っていただきます。
また、気温が高い季節では休息の合間で水分摂取をしていただきます。
できるだけご本人の希望に沿いながら、ご自宅の環境にあった内容を行い、必要に応じて福祉用具のレンタルの提案もさせていただきます。
最後に
小さな変化に気づき、日々の暮らしを整えていくことが「その人らしさ」を守る看護につながるのだと、Aさんとの関わりの中で改めて感じています。
今後も一人ひとりの声に丁寧に耳を傾けながら、安心できる生活を一緒に築いていきたいと思います。
次回は、パーキンソン病のまとめをさせていただきます。