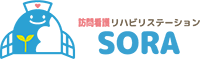在宅療養コラム~パーキンソン病編その1
パーキンソン病は国の指定難病の中でも、患者数が最も多い病気です。(令和5年度末受給者証所持者数)
特に、65歳以上では100人に約1人(10万人に1000人)と比率が高まり、高齢化に伴い患者数は増加しています。
SORAでは、現在もパーキンソン病の方の在宅生活をご支援しています。
今回はパーキンソン病の特徴について簡単にお伝えします。
どんな病気?
パーキンソン病とは、主に運動症状が現れる病気です。
原因は、中脳黒質のドパミン神経細胞の減少することで症状が出現します。
ドパミン神経が減少すると、ふるえが起きたり、体が動かしづらくなるなどの症状が出現します。
ドパミン神経細胞が減少する理由はまだ正確にはわかっていません。
ドパミン神経細胞内に特定のタンパク質(αシヌクレイン)が溜まってくることで、ドパミン神経細胞が減少すると考えられています。
黒質ドパミン神経細胞は、健常者でも加齢に伴い10年で約5%ずつ減少していくとされています。
主な症状
主な4つの『運動症状』として、
①静止時振戦(ふるえ)②動作緩慢③姿勢保持障害(転びやすい)④筋強剛(筋肉が固くなる)があります。
また、その他に『非運動症状』として、
便秘、排尿障害、睡眠障害、抑うつ(やる気が出ない、不安が強くなる)、起立性低血圧(自律神経症状)、嚥下障害があります。
パーキンソン病の重症度の指標
症状の重症度を表す指標としてホーエン・ヤールの分類があります。
5段階に分類され、運動症状と生活機能の重症度が示されています。
運動症状は一側の上下肢から発症し、その後、体側にも症状が出現し両側性となり、発症後10年経過すると、ほとんどの患者さんは姿勢保持障害が出現し、ホーエン・ヤール分類のStageⅢ以上になります。
【ホーエン・ヤールの分類】
・StageⅠ:症状は一側性で機能障害はないが、あっても軽微。
・StageⅡ:両側性の障害はあるが、姿勢保持の障害はない。日常生活、職業には多少の障害はあるが行いうる。
・StageⅢ:姿勢保持性がみられる。活動はある程度制限されるが、職業によっては仕事が可能である。機能的障害は軽度ないし中等度で、一人での生活が可能である。
・StageⅣ:要介助。重篤な機能障害を呈し、自力のみによる生活は困難となるが、支えられずに立つこと、歩くことはどうにか可能である。
・StageⅤ:全介助。介助なしでは立つことも不可能で、ベッドまたは車椅子での生活を強いられる。
パーキンソン病(指定難病)の医療費助成制度
パーキンソン病と診断されると、「指定難病患者への医療費助成制度」の適用を受けることができます。
適用を受けると、月毎の医療費の自己負担上限額が設定され、一定額以上の自己負担はしなくてよくなります。
具体的には、パーキンソン病に係る病院・薬局・訪問看護などの1ヶ月の利用費用の合計が上限額以上になっても超過分を負担する必要はありません。(詳細は「難病情報センター」のページをご覧ください。)
また、訪問看護の利用については、重症度(*)によっては介護認定を受けている方でも医療保険が優先されます。
*ホーエン・ヤール分類のStageⅢ以上であって生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度のもの
パーキンソン病の症状の特徴
パーキンソン病の特徴的な姿勢として、筋肉が固くなることで体が前傾し、首が下がり、腰が曲がり、体が斜めに傾くことが挙げられます。
『運動症状』の特徴
静止時振戦の症状では、片方の手足から始まることが多く、何もしていない時に自分の意志ではなく手足にふるえが出現します。
歩行障害の初期ではすり足となり、左右足部の横の間隔が狭く、歩幅は小さく小刻み歩行となります。
腕のフリは症状が出現する側から減少します。
歩行開始に時間がかかるようになり、前傾姿勢が増強し、歩行速度が早くなり加速歩行がみられるようになります。
『運動症状』の治療方法
運動症状に対して、主な治療方法は薬物療法と運動療法があります。
お薬はドパミン補充療法が中心となります。
効果や副作用など主治医の先生と相談しながら、薬の量や飲む回数を調整していただきます。
運動療法は筋肉が固くなる症状に対しては体幹ストレッチ(棒体操)などを実施していただきます。
また、動作緩慢から歩行障害(小刻み歩行、突進現象)も出現します。
刻み歩行がある場合は数をかぞえ、リズムをとりながら歩いたり、目印を足元に用意しそれを目標に歩いていただくと足の振り出しがスムーズになることがあります。
歩行動作と同時に注意を必要とする二重課題では、速度や歩幅の低下の増加がみられるため、会話をしたりせず目標まで歩くことに集中することが大切です。
病状は徐々に進行するため、多脚杖やピックアップ歩行器などの歩行補助具の使用を促します。
『非運動症状』の特徴と対処例
非運動症状はパーキンソン病の前駆症状として出現します。
特に便秘症状は、高頻度に合併します。
研究によると便秘を有するグループは便秘のないグループよりもパーキンソン病の発症率が4倍高いことが示されています。便秘になる原因として、腸管神経叢にαシヌクレインを含むレビー小体が出現することが考えられています。
自律神経の障害により起立性低血圧をおこします。
座位や立位になると血圧が下がり、めまいや立ちくらみをおこし、転倒骨折をするリスクがあります。
起立性低血圧に対しては、循環血液量の増加を目的に水分・塩分摂取を増やしたり、弾性ストッキングを履いていただいたりします。
パーキンソン病の方の嚥下障害の特徴として、呼気の気流が少なく咳が弱くなるため、不顕性誤嚥がみられます。
誤嚥性肺炎を予防するため、食事の形態を変えるなどの工夫が必要になります。
食べ物の認知する能力も低下するため食事をする際は集中できる環境で食べていただきます。
次回は、SORAで行っているパーキンソン病の方の症状へのアプローチをご紹介していきたいと思います。
参考資料
・難病情報センターホームページ
・パーキンソン病療養指導士テキストブック アルタ出版